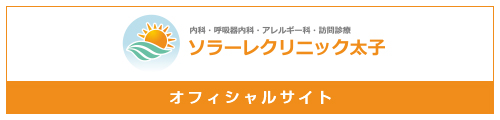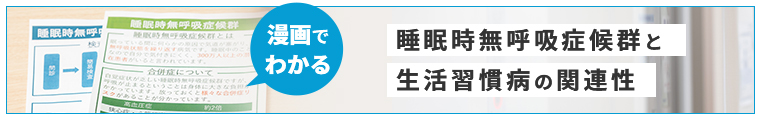- HOME>
- 健康診断・検診で異常があったら
健康診断・検診で異常があったら
健康診断を受けた後、以下のようなことでお困り・お悩みではありませんか?
- 健康診断・検診で数値の異常を指摘され、改善したい
- 要経過観察・要精密検査の結果が出たので、定期的に検査を受けたい
- 身近なクリニックで再検査を受けたい
- 健康診断・検診で異常を指摘されたが、何を表しているのかが分からない
健康診断の結果について理解したいという方や、要経過観察・要精密検査の指摘があった方は、ご自身の体に何らかの疾患が隠れている可能性があります。一度、兵庫県揖保郡太子町の『ソラーレクリニック太子』までご来院していただき、ご不安な内容をご相談ください。
結果の見方
健康診断や検診の結果通知には、数値などに応じて下記の項目が記載されています。
それぞれの項目について、対応方法を記載しておりますので、ご参考にしてください。
異常なし
○今回の健康診断では、検査結果が正常の範囲内であることを示します。
○今後も定期的に、できれば年に1回は健康診断を受けてください。
要経過観察・要再検査
○検査結果が正常の範囲ないではないものの、緊急を要するものではないことを示します。
○お時間があれば、近くのクリニックまで受診することをおすすめします。
要精密検査
○さらに詳しい検査が必要であることを示します。ただし、要精密検査を告げられたからといって、必ず異常があるわけではありません。
○不安であると思いますので、近くのクリニックまで受診し、本当に異常があるのかどうかを知るためにより詳しい検査を受けてください。
要治療
○治療が必要な異常値が確認されたことを示します。
○すぐに医療機関を受診し、適切な診断・治療を受けてください。
※健康診断や検診で採血や尿検査を実施されていると思いますが、当院でも再度検査をさせていただく場合がございます。正確な診療、診断、治療のため必要な検査ですのでご了承いただけますと幸いです。
ヘモグロビン
ヘモグロビンとは
ヘモグロビンは、赤血球の中に含まれるタンパク質の一種であり、肺で吸い込んだ酸素と結びつき、血液の流れに乗って体の隅々まで酸素を届けます。そして、各組織で不要になった二酸化炭素を受け取り、肺まで戻ってきます。
このヘモグロビンが不足すると、体が酸素不足に陥り、貧血を引き起こします。 貧血になると、動悸やめまい、息切れ、疲労感などの症状が現れることがあります。健康診断では、このヘモグロビンの量を測定することで、貧血の有無を調べます。
正常値(基準値)
男性:13.0~16.9 g/dL
女性:11.6~14.8 g/dL
異常が見られた場合に考えられる病気
低い場合(貧血): 鉄欠乏性貧血、巨赤芽球性貧血、再生不良性貧血、溶血性貧血など
高い場合(多血症): 真性多血症、脱水症、肺疾患、心疾患など
ヘモグロビンの値が基準値から外れている場合は、貧血や多血症などの疑いがあります。貧血は、酸素不足により、動悸、息切れ、めまい、疲労感などの症状を引き起こします。多血症は、血液がドロドロになることで、血栓ができやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞のリスクを高めます。ヘモグロビンの異常を指摘された場合はお気軽に、兵庫県揖保郡太子町の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。
血清クレアチニン
血清クレアチニンとは
血清クレアチニンは、筋肉の活動によって生成される老廃物です。通常クレアチニンは、血液中に放出された後、腎臓で濾過され、尿として体外に排出されます。
腎臓の機能が正常であれば、クレアチニンは効率よく排出されますが、腎臓の機能が低下すると、血液中のクレアチニン濃度が上昇します。そのため、血清クレアチニンの値は、腎臓の機能を評価する重要な指標となります。
正常値(基準値)
男性:0.6~1.1 mg/dL
女性:0.4~0.8 mg/dL
異常が見られた場合に考えられる病気
高い場合: 腎機能障害、腎不全、脱水症状、筋肉の分解亢進など
低い場合: 筋肉量が少ない、 malnutrition(栄養不良)など
血清クレアチニンの値が高い場合は、腎臓の機能が低下している可能性があります。腎臓病は初期段階では自覚症状が出にくいため、定期的な検査で早期発見することが重要です。血清クレアチニンの異常を指摘された場合はお気軽に、網干の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。
eGFR
eGFRとは
eGFR(推算糸球体濾過量)は、血液中のクレアチニン値、年齢、性別などから腎臓の機能を推定する指標です。腎臓には、糸球体と呼ばれる小さなフィルターがあり、血液を濾過して老廃物や余分な水分を尿として排出する機能があります。eGFRは、この糸球体の濾過能力を数値化したもので、腎臓病の重症度を判断する上で重要な検査値です。
正常値(基準値)
60 mL/分/1.73㎡以上
異常が見られた場合に考えられる病気
低い場合: 慢性腎臓病(CKD)、急性腎障害、糖尿病性腎症など
eGFRが低い場合は、腎臓の機能が低下している可能性があります。
eGFRが60未満の場合は、慢性腎臓病の可能性があります。
eGFRが15未満になると、末期腎不全と診断され、人工透析や腎移植が必要になる場合があります。
eGFRの低下を指摘された場合はお気軽に、兵庫県揖保郡太子町の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。
尿素窒素
尿素窒素とは
尿素窒素は、タンパク質が体内で分解される過程で生じる老廃物です。食事から摂取したタンパク質は、体内でアミノ酸に分解され、エネルギー源として利用されます。その際に生じるアンモニアは、肝臓で尿素に変換され、血液中に放出されます。そして、腎臓で濾過され、尿として体外に排出されます。腎臓の機能が低下すると、尿素窒素が血液中に蓄積され、尿素窒素の値が高くなります。
正常値(基準値)
8~20 mg/dL
異常が見られた場合に考えられる病気
高い場合: 腎機能障害、腎不全、脱水症状、消化管出血、心不全など
低い場合: 肝機能障害、 malnutrition(栄養不良)など
尿素窒素の値が高い場合は、腎臓の機能が低下している可能性があります。
また、脱水症状や消化管出血などによっても上昇することがあります。
尿素窒素の異常を指摘された場合はお気軽に、網干の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。
尿酸値
尿酸値とは
尿酸値は、細胞の核酸が分解されてできる老廃物である尿酸の血液中の濃度を示す値です。
尿酸は、プリン体と呼ばれる物質が体内で分解される過程で生成されます。プリン体は、細胞の核酸やエネルギー代謝に関わる重要な物質ですが、過剰に摂取すると尿酸値が高くなることがあります。
正常値(基準値)
男性:3.0~7.0 mg/dL
女性:2.0~5.7 mg/dL
異常が見られた場合に考えられる病気
高い場合: 高尿酸血症、痛風、腎臓病、動脈硬化など
尿酸値が高い状態が続くと、高尿酸血症となり、痛風発作を引き起こす可能性があります。痛風は、関節に尿酸の結晶が溜まり、激しい痛みや腫れを引き起こす病気です。尿酸値の高値を指摘された場合はお気軽に、兵庫県揖保郡太子町の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。
尿蛋白
尿蛋白とは
尿蛋白とは、尿中にタンパク質が排出されている状態のことです。健康な人でも、少量のタンパク質は尿中に排出されますが、腎臓に障害が起こると、通常は血液中に留まっているタンパク質が尿中に漏れ出てきます。
正常値(基準値)
陰性(-)
異常が見られた場合に考えられる病気
陽性(+): 腎臓病(ネフローゼ症候群、糖尿病性腎症、IgA腎症など)、高血圧、膀胱炎、尿路感染症など
尿蛋白が陽性の場合、腎臓の糸球体と呼ばれる部分が障害を受けている可能性があります。
腎臓病は初期段階では自覚症状が出にくいことが多いため、健康診断などで尿蛋白を指摘された場合は、精密検査を受けることが重要です。
尿蛋白の異常を指摘された場合はお気軽に、兵庫県揖保郡太子町の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。
尿糖
尿糖とは
尿糖とは、尿中に糖が排出されている状態のことです。通常、血液中の糖(ブドウ糖)は、腎臓で濾過された後、再吸収されて血液に戻ります。しかし、血糖値が非常に高くなると、腎臓の再吸収能力を超えてしまい、糖が尿中に漏れ出てきます。
正常値(基準値)
陰性(-)
異常が見られた場合に考えられる病気
陽性(+): 糖尿病、妊娠糖尿病、甲状腺機能亢進症など
尿糖が陽性の場合、糖尿病の可能性があります。糖尿病は、血糖値が高くなることで、様々な合併症を引き起こす病気です。
尿糖の異常を指摘された場合はお気軽に、網干の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。
HbA1c
HbA1cとは
HbA1c(ヘモグロビンA1c)は、赤血球中のヘモグロビンにブドウ糖が結合したものです。
血糖値が高い状態が続くと、ヘモグロビンに結合するブドウ糖の量も多くなります。HbA1cは、過去1~2ヶ月の平均血糖値を反映するため、糖尿病の診断や治療効果の判定に用いられます。
正常値(基準値)
6~6.2%
異常が見られた場合に考えられる病気
高い場合: 糖尿病、耐糖能異常など
HbA1cが高い場合は、糖尿病の可能性があります。糖尿病は、血糖値が高くなることで、動脈硬化を引き起こし、脳梗塞や心筋梗塞などの合併症を引き起こす可能性があります。HbA1cの高値を指摘された場合はお気軽に、兵庫県揖保郡太子町の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。
血糖値
血糖値とは
血糖値とは、血液中に含まれるブドウ糖の濃度のことです。ブドウ糖は、私たちが活動するためのエネルギー源として非常に重要です。食事から摂取した炭水化物は、体内で消化・吸収され、ブドウ糖に変換されます。このブドウ糖は、血液によって全身の細胞に運ばれ、エネルギーとして利用されます。
血糖値は、食事や運動、ホルモンなどの影響を受けて常に変動しています。食後には血糖値が上昇し、運動すると血糖値が低下します。また、インスリンなどのホルモンは、血糖値を一定の範囲内に保つように働いています。
正常値(基準値)
空腹時血糖値:70~109 mg/dL
異常が見られた場合に考えられる病気
高い場合: 糖尿病、ストレス、ホルモン異常など
低い場合: 低血糖症、インスリンの過剰投与など
血糖値が高い状態が続くと、糖尿病の疑いがあります。
また、血糖値が低い状態が続くと、低血糖症となり、意識障害やけいれん発作などを引き起こすことがあります。
血糖値の異常を指摘された場合はお気軽に、網干の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。
HDL-コレステロール
HDL-コレステロールとは
HDL-コレステロールは、「善玉コレステロール」とも呼ばれる脂質の一種です。コレステロールは、細胞膜やホルモンの材料となる重要な物質ですが、血液中に過剰に存在すると、動脈硬化を引き起こす原因となります。
HDL-コレステロールは、血管壁に蓄積したコレステロールを回収し、肝臓に運んで処理する働きがあります。そのため、HDL-コレステロール値が高いほど、動脈硬化を予防する効果が期待できます。
正常値(基準値)
40 mg/dL以上
異常が見られた場合に考えられる病気
低い場合: 動脈硬化、冠動脈疾患、脳卒中などのリスク増加
HDL-コレステロール値が低い場合は、動脈硬化のリスクが高くなる可能性があります。動脈硬化は脳梗塞や心筋梗塞などの命に関わる疾患を併発する可能性が高いです。HDL-コレステロールの低下を指摘された場合はお気軽に、兵庫県揖保郡太子町の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。
LDL‐コレステロール
LDL-コレステロールとは
LDL-コレステロールは、「悪玉コレステロール」とも呼ばれる脂質の一種です。コレステロールは、細胞膜やホルモンの材料となる重要な物質ですが、血液中に過剰に存在すると、動脈硬化を引き起こす原因となります。
LDL-コレステロールは、肝臓で作られたコレステロールを全身の細胞に運ぶ働きがあります。しかし、LDL-コレステロール値が高いと、コレステロールが血管壁に蓄積しやすくなり、動脈硬化を促進してしまいます。
正常値(基準値)
140 mg/dL未満
異常が見られた場合に考えられる病気
高い場合: 動脈硬化、冠動脈疾患、脳卒中などのリスク増加
LDL-コレステロール値が高い場合は、動脈硬化のリスクが高くなる可能性があります。動脈硬化は脳梗塞や心筋梗塞などの命に関わる疾患を併発する可能性が高いです。HDL-コレステロールの低下を指摘された場合はお気軽に、網干の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。
中性脂肪
中性脂肪とは
中性脂肪は、私たちが活動するためのエネルギー源となる脂質の一種です。食事から摂取した脂肪や糖質は、エネルギーとしてすぐに使われない場合、中性脂肪として体内に蓄えられます。
中性脂肪は、皮下脂肪や内臓脂肪として蓄積され、必要に応じてエネルギーとして利用されます。しかし、中性脂肪値が高い状態が続くと、肥満や高脂血症、動脈硬化などのリスクが高くなります。
正常値(基準値)
30~149 mg/dL
異常が見られた場合に考えられる病気
高い場合: 高脂血症、動脈硬化、膵炎など
中性脂肪値が高い状態が続くと、高脂血症となり、動脈硬化のリスクが高くなります。動脈硬化は脳梗塞や心筋梗塞などの命に関わる疾患を併発する可能性が高いです。HDL-コレステロールの低下を指摘された場合はお気軽に、兵庫県揖保郡太子町の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。
BNP
BNPとは
BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)は、心臓から分泌されるホルモンの一種です。心臓は、全身に血液を送り出すポンプの役割を果たしていますが、このポンプ機能が低下すると、心臓に負担がかかり、心臓の壁が圧迫されます。
心臓の壁が圧迫されると、BNPが血液中に分泌されます。BNPには、血管を拡張させて心臓の負担を軽減したり、尿の排出を促して体内の水分量を調整したりする働きがあります。
心不全になると、心臓のポンプ機能が低下し、心臓に負担がかかるため、BNPの分泌量が増加します。そのため、BNPは心不全の診断や重症度を評価するための重要な指標となります。
正常値(基準値)
4 pg/mL以下
異常が見られた場合に考えられる病気
高い場合: 心不全、心筋梗塞、弁膜症など
BNPの値が高い場合は、心不全の可能性があります。心不全は、心臓のポンプ機能が低下し、全身に血液を送り出すことができなくなる病気です。BNPの高値を指摘された場合はお気軽に、網干の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。
AST/ALT
AST(GOT)/ALT(GPT)とは
ST(GOT)とALT(GPT)は、アミノ酸の代謝に関わる酵素で、主に肝臓の細胞に存在しています。
肝臓は、栄養分の代謝や解毒、胆汁の生成など、様々な働きを担う重要な臓器です。しかし、肝炎ウイルスに感染したり、アルコールの飲み過ぎや肥満によって肝臓に負担がかかり続けると、AST(GOT)やALT(GPT)が血液中に漏れ出てきます。そのため、AST(GOT)やALT(GPT)の値は、肝臓の機能を評価するための指標となります。
正常値(基準値)
AST(GOT):10~40 U/L
ALT(GPT):7~40 U/L
異常が見られた場合に考えられる病気
高い場合: 肝炎、脂肪肝、アルコール性肝障害、肝硬変など
AST(GOT)やALT(GPT)の値が高い場合は、肝臓が傷つき肝機能が低下している可能性があります。AST(GOT)やALT(GPT)の異常を指摘されたらお気軽に、兵庫県揖保郡太子町の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。
γGTP
γ-GTPとは
γ-GTPは、γ-グルタミルトランスペプチダーゼという酵素の略称で、主に肝臓や胆道に存在しています。
γ-GTPは、細胞膜に存在し、アミノ酸の輸送やグルタチオンの代謝に関与しています。アルコールの摂取や薬物の代謝、胆汁の流れが悪くなることなどによって、γ-GTPの値が上昇することがあります。
γ-GTPは、肝臓や胆道の傷つき具合を反映する指標となりますが、AST(GOT)やALT(GPT)よりも感度が高く、軽度の損傷でもγ-GTP値が上昇することがあります。
正常値(基準値)
男性:10~50 U/L
女性:7~30 U/L
異常が見られた場合に考えられる病気
高い場合: 脂肪肝、アルコール性肝障害、肝炎、胆石、胆道がん、膵臓がんなど、γ-GTPの値が高い場合は、肝臓や胆道に異常がある可能性があります。γ-GTPの異常を指摘された場合はお気軽に、兵庫県揖保郡太子町の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。
白血球
白血球とは
白血球は、体内に侵入してきた細菌やウイルスなどの異物から体を守る免疫細胞です。血液中に存在する白血球は、体内の「警察官」のような役割を果たし、常に体内をパトロールして、細菌やウイルスなどの異物を発見すると、攻撃して排除します。
白血球には、好中球、リンパ球、単球、好酸球、好塩基球など、様々な種類があり、それぞれ異なる役割を担っています。
- 好中球: 細菌や真菌を貪食する
- リンパ球: ウイルスやがん細胞を攻撃する
- 単球: 体内に侵入した異物を処理する
- 好酸球: アレルギー反応に関与する
- 好塩基球: 炎症反応に関与する
正常値(基準値)
3,500~9,000 /μL
異常が見られた場合に考えられる病気
高い場合(白血球増加症): 感染症、炎症性疾患、白血病など
低い場合(白血球減少症): 再生不良性貧血、薬剤の副作用、自己免疫疾患など
白血球の値が基準値から外れている場合は、感染症や炎症、血液疾患などの疑いがあります。
白血球増加症では、発熱、倦怠感、リンパ節の腫れなどの症状が現れることがあります。
白血球減少症では、免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなる可能性があります
白血球の異常を指摘された場合はお気軽に、網干の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。
赤血球
赤血球とは
赤血球は、血液中で最も多い細胞で、全身に酸素を運ぶ役割を担っています。赤血球は、ドーナツのような形をしており、中央がくぼんでいます。この形は、赤血球が狭い血管を通過する際に変形しやすく、酸素を効率よく運ぶのに役立っています。
赤血球には、ヘモグロビンと呼ばれるタンパク質が含まれており、このヘモグロビンが酸素と結合することで、酸素を全身に輸送します。ヘモグロビンは、鉄を含むタンパク質で、酸素と結合すると鮮やかな赤色になります。そのため、血液は赤く見えます。
正常値(基準値)
男性:450万~550万 /μL
女性:400万~500万 /μL
異常が見られた場合に考えられる病気
高い場合(多血症): 真性多血症、脱水症、肺疾患、心疾患など
低い場合(貧血): 鉄欠乏性貧血、巨赤芽球性貧血、再生不良性貧血など
赤血球の値が基準値から外れている場合は、多血症や貧血などの疑いがあります。
多血症は、血液がドロドロになることで、血栓ができやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞のリスクを高めます。
貧血は、酸素不足により、動悸、息切れ、めまい、疲労感などの症状を引き起こします。
赤血球の異常を指摘された場合はお気軽に、兵庫県揖保郡太子町の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。
電解質
電解質とは
電解質は、体内の水分バランスや神経・筋肉の機能を維持するために重要な役割を果たすミネラルです。電解質は、水に溶けると電気を帯びる性質があり、体内でイオンとして存在しています。
主な電解質には、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、塩素などがあります。
- ナトリウム: 体内の水分量を調節する
- カリウム: 神経や筋肉の働きを調節する
- カルシウム: 骨や歯の形成、筋肉の収縮に関与する
- マグネシウム: 酵素の働きを助ける
- 塩素: 体液のpHバランスを維持する
電解質のバランスが崩れると、脱水症状や不整脈、筋肉の痙攣など、様々な症状を引き起こす可能性があります。
正常値(基準値)
ナトリウム:135~145 mEq/L
カリウム:3.5~5.0 mEq/L
カルシウム:8.5~10.5 mg/dL
異常が見られた場合に考えられる病気
ナトリウム異常: 脱水症、腎不全、心不全など
カリウム異常: 腎不全、心不全、薬剤の副作用など
カルシウム異常: 副甲状腺機能亢進症、副甲状腺機能低下症、ビタミンD欠乏症など
電解質のバランスが崩れると、脱水症状や不整脈、筋肉の痙攣など、様々な症状を引き起こす可能性があります。
電解質の異常を指摘された場合はお気軽に、網干の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。
尿蛋白クレアチニン比
尿蛋白クレアチニン比(UPCR)とは
尿蛋白クレアチニン比(UPCR)は、尿中の蛋白質とクレアチニンの比率を測定する検査です。
尿蛋白は、腎機能を反映する指標となりますが、尿の濃縮度によって変動するため、1日の尿蛋白量を測定する必要があります。しかし、1日の尿蛋白量を測定するには、24時間分の尿をする必要があり、患者さんの負担が大きいです。
そこで、尿蛋白クレアチニン比(UPCR)が用いられます。UPCRは、1回の尿検査で測定でき、尿の濃縮度の影響を受けにくいという利点があります。
正常値(基準値)
15 g/gCr未満
異常が見られた場合に考えられる病気
い場合: 腎臓病(ネフローゼ症候群、糖尿病性腎症、IgA腎症など)
尿蛋白クレアチニン比が高い場合は、腎臓の糸球体と呼ばれる部分が障害を受けている可能性があります。
尿蛋白クレアチニン比の高値を指摘された場合はお気軽に、兵庫県揖保郡太子町の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。
尿潜血
尿潜血とは
尿潜血とは、尿中に肉眼では見えない程度の微量の血液が混じっている状態のことです。尿潜血は、試験紙を用いた簡単な検査で調べることができます。
健康な人でも、激しい運動や長時間の立ち仕事などによって、一時的に尿潜血が陽性になることがあります。しかし、特に原因もなく尿潜血が陽性になる場合は、腎臓、尿管、膀胱、尿道など、尿路のどこかに異常があるサインである可能性があります。
正常値(基準値)
陰性(-)
異常が見られた場合に考えられる病気
陽性(+): 腎臓病、尿路結石、膀胱炎、尿路感染症、前立腺肥大症など
尿潜血が陽性の場合、腎臓、尿管、膀胱、尿道など、尿路のどこかに異常がある可能性があります。
尿潜血を指摘された場合はお気軽に、網干の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。
グリコアルブミン
グリコアルブミンとは
グリコアルブミンは、血液中のタンパク質であるアルブミンにブドウ糖が結合したものです。
血糖値が高い状態が続くと、血液中のブドウ糖がアルブミンに結合し、グリコアルブミンが生成されます。アルブミンの寿命は約2~3週間であるため、グリコアルブミン値は過去2~3週間の平均血糖値を反映します。
HbA1cと同様に、グリコアルブミンも糖尿病の診断や治療効果の判定に用いられますが、HbA1cは赤血球の寿命に影響されるため、貧血などがある場合は、グリコアルブミンの方が正確に血糖コントロール状態を反映できる場合があります。
正常値(基準値)
0~17.0%
異常が見られた場合に考えられる病気
高い場合: 糖尿病
グリコアルブミン値が高い場合は、糖尿病の可能性があります。糖尿病は動脈硬化を引き起こし、脳梗塞や心筋梗塞など命に関わる疾患を併発する可能性が高くなります。グリコアルブミンの異常を指摘されたらお気軽に、兵庫県揖保郡太子町の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。
総コレステロール
総コレステロールとは
総コレステロールは、血液中のコレステロールの総量を示す値です。コレステロールは、細胞膜やホルモンの材料となる重要な脂質ですが、血液中に過剰に存在すると、血管壁に蓄積して動脈硬化を引き起こす原因となります。
コレステロールには、HDL-コレステロール(善玉コレステロール)とLDL-コレステロール(悪玉コレステロール)の2種類があります。HDL-コレステロールは、血管壁に蓄積したコレステロールを回収して肝臓に戻す働きがあり、動脈硬化を予防する効果があります。一方、LDL-コレステロールは、血管壁にコレステロールを運び、動脈硬化を促進する働きがあります。
正常値(基準値)
150~219 mg/dL
異常が見られた場合に考えられる病気
高い場合: 高コレステロール血症、動脈硬化など
低い場合: 甲状腺機能亢進症など
総コレステロールの異常を指摘された場合はお気軽に、網干の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。
総タンパク
総タンパクとは
総タンパクは、血液中のタンパク質の総量を示す値です。タンパク質は、筋肉、臓器、酵素、ホルモンなど、体の様々な組織を構成する重要な成分です。血液中のタンパク質は、主にアルブミンとグロブリンからなります。アルブミンは、血液の浸透圧を維持したり、栄養分やホルモンを運搬したりする働きがあり、グロブリンは、免疫機能に関与する抗体などを含みます。そのため総タンパクの値は、栄養状態を反映したり、肝臓・腎臓の機能を反映する指標になります。
正常値(基準値)
5~8.0 g/dL
異常が見られた場合に考えられる病気
高い場合: 脱水症状、多発性骨髄腫など
低い場合: 栄養不良、肝硬変、ネフローゼ症候群など
総タンパクの異常を指摘された場合はお気軽に、兵庫県揖保郡太子町の『ソラーレクリニック太子』までご来院ください。